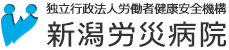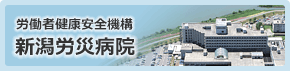C型肝炎
はじめに
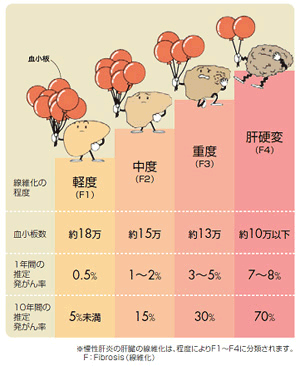
山梨県特別顧問・東京大学名誉教授 小俣政男先生監修の“肝胆チェック”から、許可を得て転載しました。
肝炎を起こすウイルスには、主にA、B、C、D、E型の5種類があります。感染すると慢性肝炎、肝硬変、肝癌へと進むことがあるB、C型は特に注意を必要とします。日本人の肝癌死亡者数は、約3万5000人で、肺癌、胃癌、大腸癌に次いで第4位です。この肝癌死亡者の80%がC型肝炎によるものとされています。
型慢性肝炎の診断
HCV血症の証明、肝機能の評価(活動性、進行度)が中心となります。慢性肝炎の段階では、自他覚症状は乏しいのが特徴です。
HCV感染の証明は、血液検査のHCV抗体、HCV-RNAの測定で行います。
肝病変の評価は、血液検査、画像検査から行います。
血液検査では、次の様な評価を行います。
- 肝病変の活動性:AST、ALTの増減が肝細胞障害を反映
- 肝機能、合成能:ビリルビン、アルブミン、コリンエステラーゼ、プロトロンビン時間など
- 肝病変の進行度:肝線維化マーカー(ヒアルロン酸、Ⅳ型コラーゲン7S)
- 腫瘍マーカー:AFP、PIVKA-Ⅱ
- HCVゲノタイプ、HCV-RNA量 :インターフェロン治療を考慮するとき
画像検査では、次の様な検査を行います。
- 腹部エコー:慢性肝炎は、6ヵ月、肝硬変は、3-4ヵ月に一度行います。
- CT、MRI検査:腹部エコーが基本ですが、CT、MRIを組み合わせることで、肝細胞癌の早期診断能、質的診断能が上がることが示されています。
- 上部消化管内視鏡検査:肝の線維化が進行すれば食道、胃静脈瘤が出現します。内視鏡検査を定期的に行い、静脈瘤の発見と経過観察を行います。
- 肝生検:慢性肝炎の時、肝線維化を評価する上で、肝組織診断を上回る情報はありません。
治療の選択
C型慢性肝炎の治療はインターフェロン治療(可能ならリバビリン併用)が第一選択です。
インターフェロン治療は、HCVの種類、HCV-RNA量により、用いるインターフェロンの種類や併用薬(リバビリン、テラプレビルなど、)を考慮します。治療開始後も、ウイルス量の変化を評価しながら、インターフェロン治療期間を検討します。(主に48-72週間)。
当院では、インターフェロン投与延長を少なくする目的で、β-IFN(フェロン)先行投与+Peg-IFN、リバビリン投与を行う場合もあります。また、患者さんの背景、年齢、合併症の有無などにより、インターフェロン治療を行わないこともあります。
リバビリン併用インターフェロン治療を行ったが著効が得られなかった患者さん、また、インターフェロン治療が併存疾患、年齢などによって適応外の患者さんでは、内服薬(ウルソ、グリチロンなど)や注射薬(強力ミノファーゲンC)、瀉血(しゃけつ)療法(体内の鉄を少なくする目的で血液を捨てる治療)などがあります。