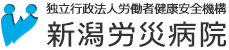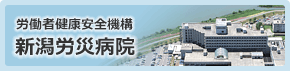炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎について
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜(最も内側の層)にびらんや潰瘍ができる大腸の炎性疾患です。特徴的な症状としては、下血を伴うまたは伴わない下痢と腹痛です。病変は直腸から連続的に、そして上行性(口側)に広がる性質があり、最大で直腸から結腸全体に拡がります。この病気は病変の拡がりや経過などにより下記のように分類されます。
- 病変の拡がりによる分類:全大腸炎、左側大腸炎、直腸炎
- 病期の分類:活動期、寛解期
- 重症度による分類:軽症、中等症、重症、激症
- 臨床経過による分類:再燃寛解型、慢性持続型、急性激症型、初回発作型

軽症

中等症

重症
まず、患者さんの最初の訴えとしては、経過の長い腹痛、下痢、下血等の症状です。以上の症状のある方に大腸内視鏡検査を施行します。上の写真の様な粘膜がみられ、感染等の影響が否定されましたら潰瘍性大腸炎と診断します。
次に治療ですが、治療指針(平成21年度 潰瘍性大腸炎治療指針改訂案 最終決定版など)にのっとり、治療をすすめて参ります。その中で特にステロイド治療に抵抗性の患者様に対しては、顆粒球除去療法(G-CAP)や生物学的製剤(インフリキシマブ、商品名レミケード)投与、免疫抑制剤(AZA、6-MP、CyA等)の併用等の治療も試みております。
潰瘍性大腸炎が寛解された方には、外来通院にて維持療法の継続を行いフォローアップの大腸内視鏡検査も適宜施行しております。
クローン病について
クローン病とは1932年にニューヨークのマウントサイナイ病院の内科医クローン先生らによって限局性回腸炎としてはじめて報告されました。クローン病は主として若年者にみられ、口腔にはじまり肛門にいたるまでの消化管のどの部位にも炎症を引き起こす病気です。びらんや潰瘍(粘膜が欠損すること)が起こりえますが、小腸の末端部が好発部位で、非連続性の病変(病変と病変の間に正常部分が存在すること)が特徴です。それらの病変により腹痛や下痢、血便、体重減少などが生じる病気です。潰瘍性大腸炎と比較して患者数は少ないものの、近年増加傾向にあります。
クローン病についても潰瘍性大腸炎と同様に、大腸内視鏡または上部消化管内視鏡により診断の上、治療指針(平成21年度 クローン病治療指針改訂案 最終決定版)にのっとり治療を行っております。


特に生物学的製剤であるインフリキシマブ(レミケード)を使用した早期の寛解導入を試みており、外来化学療法室にて継続的な外来投与を可能にしております。

外来化学療法室です。レミケードの投与を行います。